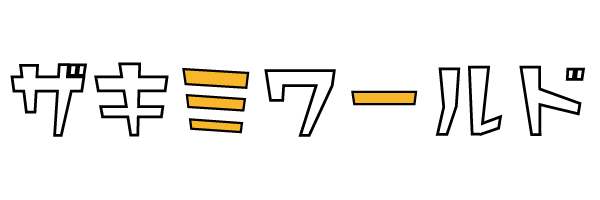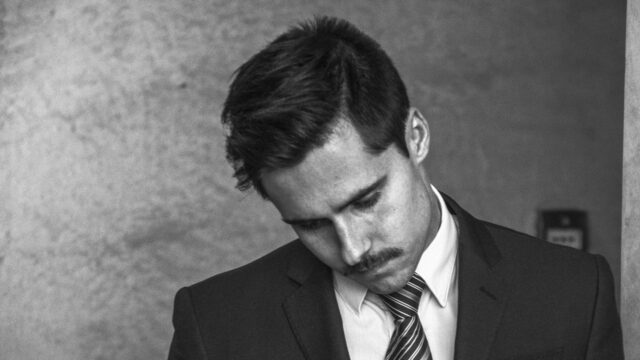こんにちは。
就活を始めている方は恐らく一度はグループディスカッションを行ったことがあるのでしょうか。
今年はコロナの影響もありオンラインで開催されることが多く特に難しさを感じている人も多いのではないでしょうか?
今回はそんなあなたのためにグループディスカッションの目的やオンラインでグループディスカッションを行う際にどんなことに気を付ければ良いのかを紹介していきます。
グループワークが苦手という方は是非参考にしてみてください。
なぜグループディスカッションを行うのか

さてそもそも何故グループディスカッションを行うのでしょうか?
グループディスカッションでは周囲の人間と議論を重ねながら時間内に一つの結論を導き出さなくてはいけません。
そのため、「簡潔に」「筋の通った」話ができるかが顕著に現れます。
書類選考や面接では判断しにくい論理的思考力を評価するためのヒントになるため多くの企業がグループディスカッションを実施しています。

グループディスカッションの進め方とコツ

➀役割を決める
グループディスカッションにおいてざっくり役割を決めておくことは短い時間で円滑に議論を進めるうえで重要なことです。
- 司会進行
- 書記
- アイデアマン
- 傍観役
主に上の4つの役割はどんなグループディスカッションでも必要になってくる役割です。
どの役割が評価されるなどは特にありません。
自分が最も得意/自分らしさを出せる役割を見極めて最初の1分程度でチームでの立ち位置を定めるようにしましょう。
②時間配分を決める
時間配分を決めておくことも重要です。
グループディスカッションとはうまく意見がまとまらないものです。
そんな時に一番避けたいのが頑張ってまとめようとしすぎて時間が足りなくなってしまうことです。
そんなことを防ぐためにも大体何分かけて一つ一つの議論を行うのかという大枠を決めておくようにしましょう。
➂議論の落としどころを事前に決定
続いて意識してほしいのが議論の落としどころを決めるということです。
正直これが一番重要といってしまっても過言ではありません。
グループのメンバーはそれぞれ自分の意見が最も効果的であると信じて発言をしています。
それ自体は全く悪いことではありませんし、そうした意見がたくさん出るのは良いグループディスカッションの証拠です。
ですが、課題に対してなにを判断基準に最終的なアウトプットを出すかだけは最初に決めておくようにしましょう。
各個人の判断軸が違うことには一向にグループがまとまることはありません。
そこで判断軸だけは最初に統一しておくことで円滑がグループディスカッションを円滑に進めることを助けます。
④時間を意識しながら議論を進める
ここまでで紹介した3つのことが定まったらあとは最初に立てた計画にそってグループディスカッションを進めていきましょう。
ここで注意すべくは時間を必ず意識することです。
いくら計画を立てても計画通りに物事が進まなくては全く意味がありません。
そこで議論の途中でも計画通りに進むくらいストイックに時間を意識して議論を進めるように努めましょう。
⑤発表の内容をまとめる
終盤になってきたら発表の内容をまとめる作業が必要になります。
ここで大切なのは誰がどの部分をまとめるかの役割を決めてまとめるということです。
現在はオンラインでのグループディスカッションが主流なのでグーグルスライド等を活用して皆が協力して内容をまとめられるようにすると効率よく質の高い発表を行うことが可能になります。
くれぐれも書記の人に任せるということだけはしないようにしましょう。
⑥発表者を決めて発表練習
最後に重要なのが発表の練習をするということです。
ぶっつけ本番で発表を行ってしまっては上手く伝えたいことが伝えられなかったり、言葉が詰まって時間を有効活用できなくなってしまうといったトラブルが発生してしまうかもしれません。
そこで必ず時間内に発表練習を行う時間を確保してぶっつけ本番になるということだけはないようにしましょう。
以上のことを気を付けておけば僕の経験上グループディスカッションは上手くいくので参考にしてみてください。

意見を主張するときに意識すべきこと

根拠をはっきりと伝える
まず自分の意見を主張する際には必ず根拠をはっきりさせるようにしましょう。
グループワークで他の参加者が意見をする際に毎回思うことは「なんでそう思った⁉」です。
すごく良い意見だけどその根拠の部分が良く分からず何とも言い難いと思うことが多々あります。
グループのメンバーだけでなく人事の人に自分の意見を主張するためにも根拠も合わせて主張することを意識してみてください。
定量的なデータを参考にする
続いて重要なのは定量的なデータに基づいた主張を心掛けるということです。
根拠を合わせた方が良いといいましたが根拠が主観に基づいたものだとどうしても突っ込みどころが満載になってしまいますし、主観は人それぞれ違うものなので納得感を与えにくくなってしまいます。
定量的なデータという絶対的なものを用いて主張するだけで説得力が格段に上がるので余裕がある際には意識してみてください。
あまり発言できていない人に話を振る
あなたがもし発言が得意なタイプな人であれば発言ができていない人に話を振ってあげるということも大切な仕事になります。
そして外から静かに見ている人の方がグループの状況がつかめているものです。
自分が発言をしたい気持ちをグッと抑えてあまり発言できていない人に振ってあげることで新たな気づきが生まれるかもしれません。
周囲を見て発言を促すこともグループディスカッションにおいては大切なことです。
他人の意見プラスαでもよい(根拠大切)
最後にあまり発言が得意でない人向けに自分の意見を発信する方法を紹介します。
もし自分が何かを発言するのが得意でなくても、人の意見に対してその意見良いなと思うことはあるはずです。
そんなときにどの意見が良いと思ったかと、なぜその意見を支持するのかの理由を発言するようにしましょう。
この時に注意すべきは根拠をしっかりと伝えることです。
ただ「○○が良いと思います。」ではあなたの人間性が全く分かりません。
前後に根拠をつけることであなたがどんな人かが面接官にも伝わるはずなのでそこだけは忘れないようにしましょう。
注意すべき点

自分だけが話しすぎない
グループディスカッションでは自分の能力を主張したくなりどうしても沢山話したくなってしまうかもしれません。
グループディスカッションはあくまでもチームで行うものです。
仮に企業が個人のポテンシャルだけを見たいのであればグループディスカッションを実施する意味がありません。
グループでどのような役割を担うかを見ることが目的のグループディスカッションでは企業の人に自分がどんな役割の人間かをアピールしてください。
グループワークでは発言量ではなく、発言の質を意識してみましょう。
目的を見失わない
自分の意見を伝えるのではなく、グループで最適な解を出すことがグループディスカッションにおける目的です。
ただ自分の優秀さをアピールすればよいというわけではありません。
個人の能力は面接やWebテスト等で測ることが可能なのでそういった場でアピールするようにしましょう。
グループディスカッションでは他の人の意見を取り入れながらどのように最適解を導き出すかが重要です。
「こんな短時間でグループをまとめるなんて無理だろ」という気持ちをグッと抑えてグループディスカッションの目的を忘れずに取り組むようにしましょう。
肯定的な意見を心掛ける
最後に肯定的な意見を心掛けるようにしましょう。
グループディスカッションを円滑に運営するためには周囲のメンバーに気持ち良く話してもらうことも一つ重要なことです。
否定的な意見を言ってばかりでは周囲のメンバーが意見を発信しにくくなってしまいます。
自分が評価される確率を上げるためにはまずグループディスカッション自体が円滑に進んでいることがまずは重要です。
そのためにもどんな意見でも否定するのではなく、良い部分に着目をして肯定的な意見を心掛けてグループディスカッションを円滑に進めるための潤滑油になることを意識してみましょう。
まとめ
いかがでしたか?
オンラインでの選考が主流になってきた今、グループディスカッションの進行は非常に難しいものかもしれません。
この記事を見て何となくグループディスカッションを円滑に進めるポイントを掴めた方は是非次回から実践してみてください。
最初から上手くできなくても毎回少しづつ意識すれば結果は変わります。
あなたの就活が上手くいく力になれれば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。